2025.04.23
支援としての趣味の語り合い
お互いにどうやって関係を作っていいのかがむつかしく感じられるとき,そこを乗り越えるコツは意外と単純な事もある,という話です。もちろん「障害者」と「支援者」の関係も同じです。
みんなの大学校の授業「対話と支援」では,最初に「私の趣味」を語り合うコーナーを設けてみました。
始めは授業の出だしに対話がしやすいようにアイスブレーキング程度のつもりもあって比較的軽い気持ちで始めたのですが,やってみるとこれが大変大きな意味を持つことがわかり,アイスブレーキングどころか,それだけで授業が終わってしまう状態です。
趣味について,私は去年から韓国のテレビで大ブレークをしている「日韓歌王戦」の話をしました。日韓は今,お互いに強い親しみと強い反感と,その両方が入り混じった状態になっているわけですが,私はずっと「違う文化の人同士がどうやって違いを理解して共生しているか」についての理論的・実践的な国際共同研究を続けてきて,韓国の共同研究者のシム・ヒョンボさんにこの「日韓歌王戦」のことを教えてもらい,大変に興味を持ったのです。
日本人と韓国人が,理屈の言葉ではお互いに理解や共感がむつかしいことが多いのですが,この番組の中ではお互いの歌に深く心を揺り動かされ,強い共感の関係ができるんです。音楽は国境を超える,という言葉がありますが,全くそのまんまです。
同じことが実は自閉=定型間でも起こります。周囲と上手く関係が作れずにずっとつらい思いをしてきた自閉系の人が,音楽を通して人々と共感しあえて救われる,といったことがやっぱり起こるんですね。
知的な遅れを強く伴う自閉系の青年と,リズムを合わせて「声(よく奇声と言われるものです)」のをやりとりをしていくことで,コミュニケーションが開かれ始めたりする,といった体験も私はします。
やっぱりお互いになかなか理解がむつかしいもの同士,自分にとって心地よかったり大事に感じるものを「共有する」という体験が,人と人をつなぐ大事なルートになるんだろうと思えます。
今日の授業でも同じでした。今日お話しいただいた方は大好きなテレビ番組の話をしてくださいました。なんだ,単なるテレビ番組の趣味の話か,と思われるかもしれません。ところがその番組への思い,なぜそれが好きになったのか,といったお話を聞いていくと,細かくは書けませんけれど,すごいんです。その番組の物語を通して,登場人物の葛藤や,その中での成長に共感したり,学んだり,またその番組を共有する家族との関係が変わっていったり,そして引きこもりだった自分の世界が広がっていったり。
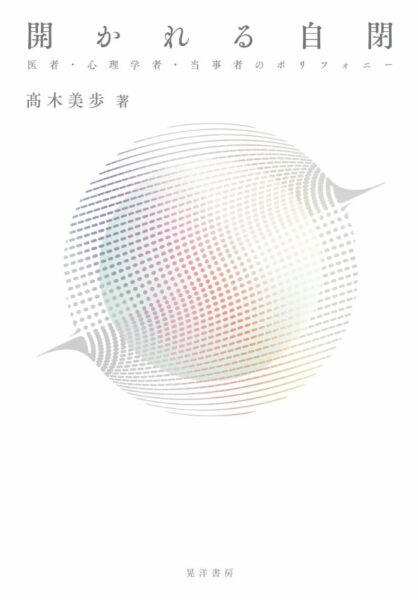 決して大げさではなく,そこにその方の苦しみや悲しみ,またそれを乗り越える喜びなど,その人の「人生」が見えてくるんですね。
決して大げさではなく,そこにその方の苦しみや悲しみ,またそれを乗り越える喜びなど,その人の「人生」が見えてくるんですね。
その「人生」を感じて,その話を聞いている私たちがまた自分の「人生」のいろんなことを思い出して語り合うことになります。そうやってお互いの人生への思いが重なり合って豊かになっていく。

今,自閉当事者で客員研究員にもなってくださっている,立命館大学の研究者&支援者の髙木美歩さんが先月末に出版された「開かれる自閉:医者・心理学者・当事者のポリフォニー」をじっくりと読み込んでいるところなのですが,あらためて心の底から感じることがあります。それは「障がい」というのは,「○○ができない」みたいなことが問題なんじゃないということです。「○○ができない」ことが,その人の生きづらさにつながってしまう状況があること,そしてその人が生きていくことについてのたくさんの「悩み」につながってしまうこと,そのこと自身が問題なんだということです。
だから,支援というのは,その「人生の大変さ」をどうやって共有し,一緒に乗り越えていけるかを考える事なんだと思えるわけですね。
その視点からいえば,趣味の語り合いには,その中にその人の喜びも悲しみも,怒りも絶望も,そして希望も見えてきます。そういう「人生」がお互いに共有される場となるんですね。そのことを強く感じています。そして生きづらさに苦しんでいる障がい者のみなさんの支援には,それが一番の足場になるような気さえしています。
人と大事なものが共有できたとき,その人は支えられる。今後この「趣味の語り合い」の授業がどう展開するか,ちょっと楽しみです。
- 「当事者視点を大事に」ということの具体的な形
- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信
- 感じ方の違いを超える対話的支援
- 支援を当事者視点から行うって何のこと?
- 支援としての趣味の語り合い
- R君の積み木(13) 調整する力の育ち
- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生
- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある
- 自閉系の方がマニアックになる時
- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる
- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと
- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ
- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす
- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる
- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ
- 間違いではなく,視点が違うだけ
- 今年が皆さんにとって良い年でありますように
- 母子分離と不安 ③
- 母子分離と依存 ②
- 母子分離と依存 ①



投稿はありません