2024.04.25
「コミュ力低い」で解雇は無効という判決
「コミュ力低い」で解雇は無効 未払い賃金の支払い命じる判決という記事を見ました。
今月から「合理的配慮」が法的な義務となりました。社会が「障がい者」に「健常(定型)社会に合わせる努力」を一方的に要求するのではなく、その人の得意を活かし、不得意を配慮で補ってその人なりに活躍してもらう、お互いの多様性を前提にした共生関係づくりの方向へと、世界が大きく変わりつつあります。
その中で、「コミュ力の低さ」を理由の一つとした解雇が無効であるという判決が出始めたわけです。
発達障がい当事者研究の熊谷さんや綾屋さんは自閉を「コミュニケーション障がい」ということを次のように批判しています。「日本人とアメリカ人のコミュニケーションがうまくいかないとき、「日本人がコミュ障だ」というのはへんでしょう?」
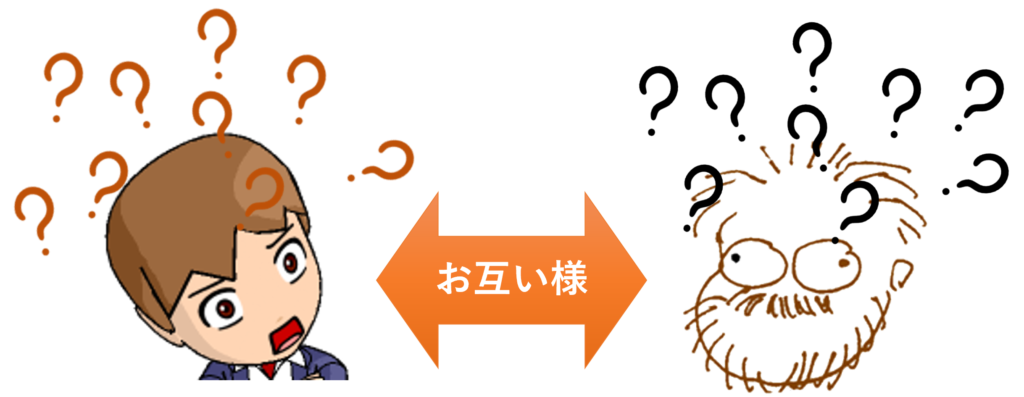
たしかに自閉系の人は定型的なコミュニケーションの意味をうまく捉えられずに対応できないことが良くあります。でも逆に定型は自閉的なコミュニケーションを理解できず(その点は私も含めてのいわゆる「専門家」も全く一緒であることは、逆SSTの実践でもはっきりしています)、その意味では本当は「お互い様」であることはますますはっきりしてきています。「コミュ障」は「お互いの間」に「お互いの理解しにくさ」として生じていることです。
だからお互いに相手のことが理解しにくいもの同士、一緒に努力することが求められているわけですね。その視点からの支援を研究所では「対話的支援」という言葉でも表現します。
この記事は、「合理的配慮」の法制化に加え、今まで主流だった「医学モデル」から、「社会モデル」へと障がいへのとらえ方や支援の考え方が大きく転換していることを示す重要な例の一つでしょう。
- 「当事者視点を大事に」ということの具体的な形
- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信
- 感じ方の違いを超える対話的支援
- 支援を当事者視点から行うって何のこと?
- 支援としての趣味の語り合い
- R君の積み木(13) 調整する力の育ち
- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生
- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある
- 自閉系の方がマニアックになる時
- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる
- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと
- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ
- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす
- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる
- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ
- 間違いではなく,視点が違うだけ
- 今年が皆さんにとって良い年でありますように
- 母子分離と不安 ③
- 母子分離と依存 ②
- 母子分離と依存 ①



投稿はありません