2019.09.01
最新の芸術絵画
またもやニューヨークネタです。
以前ご紹介したSHEDに展示されていた「最新」の絵画(?)です。(※)

近寄ってみると、ボールペンか何かでひたすら細かく文字を書き込んであります。
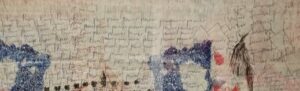
子どもの落書き?とも思えるような「作品」ですね。こういう「作品」が数枚、かなりの広いスペースを使って天井からぶら下げられていました。
昨年(2018年)、仙台で開かれた発達心理学会に、ブルーナーの理論に関するミニシンポのコメンテーターとして声をかけていただいて行ったとき、終了後の飲み会でご一緒した滋賀県立大の細馬宏通さんに紹介されて、ちょうどその時東北大の近くで開かれていた障がい者の作品展を勧められて見に行ったことがありました。
私が大学院生の頃、理学部の自然人類学教室の伊谷純一郎先生のゼミに出させていただいていた時に、そこで細馬さんが別のゼミからやって来て「エレベーター内の会話の棲み分け」の研究を発表されていたのを聞いて、面白い研究してる人がいるなとつよく印象に残っていました。何しろ当時の重たいビデオを片手で掲げ、エレベーター内の人たちの会話を記録するという、他で見たことも聞いたこともないスタイルの研究でした。
今では会話分析研究で世界的にも活躍されていますが、じつに多才な方で、シンガーソングライターとしても活躍されたり、知り合いのプロのミュージシャンたちと一緒に自閉症の方たちと即興的な演奏活動を行ったりしています。何しろ小さな型にはまる人ではありません。
それはさておき、紹介して頂いた作品展はいろんな点でとても面白いものでした。中には上の作品のように、白い服などにびっしり文字を書き込むような作品もあり、今回ニューヨークの作品を見て、「仙台で見たあれは最先端の芸術じゃん」と妙に感心して面白くなってしまいました(正直、私にはそれに感心しても感動する最先端の芸術感覚は欠如しているのですが(笑))。
私がその作品展で特に興味をひかれたもののひとつは、作品を作っている様子を新進気鋭の映像作家が撮影して編集した映像でした。
知的障がいと思われる作家や強い自閉の作家などの製作過程や監督とのやりとりが写っているのですが、みんな本当に生き生きとしていて、幸せそうに感じられたんですね。自閉症の人は人との共感関係を求めない、といった誤解も少なくないと思いますが、この映像を見ればそういう見方がいかにも現実離れした決めつけだと感じられると思います。
一人の自閉の作家は、自閉の人らしさを感じさせる細かい丁寧な「こだわり」の作品を作ってファイリングしているのですが、それを自室を訪れたスタッフに一つ一つめくって嬉しそうに見せています。作品を作ることも、それを人に見てもらうことも、その人にとっては大きな喜びであることが伝わってきます。
そんな世界を一緒に作っている家族の方も、そういう創作活動を世の中と繋いでいる方たちも、いいことしてるなあと素直に思えます。
※ cited by courtesy of the Shed, N.Y.
- 感じ方の違いを超える対話的支援
- 支援を当事者視点から行うって何のこと?
- 支援としての趣味の語り合い
- R君の積み木(13) 調整する力の育ち
- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生
- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある
- 自閉系の方がマニアックになる時
- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる
- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと
- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ
- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす
- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる
- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ
- 間違いではなく,視点が違うだけ
- 今年が皆さんにとって良い年でありますように
- 母子分離と不安 ③
- 母子分離と依存 ②
- 母子分離と依存 ①
- 支援者こそが障がい者との対話に学ぶ
- 「笑顔が出てくること」がなぜ支援で大事なのか?



投稿はありません