2023.01.05
今年もよろしくお願いいたします
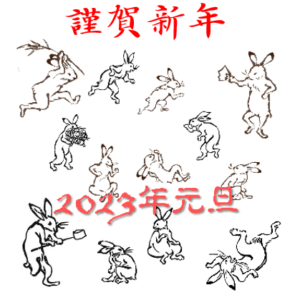
発達支援研究所は,外側から障がいを理解するばかりでなく,むしろ当事者の視点を大事に,支援者と障がい当事者が一緒に障がいを理解し,支援を考えるという工夫を続けています。日々の研修や事例検討で,現場の皆さんと一緒に実践的にその問題を考え続けてきています。昨年も本当に学ぶことの多い一年でした。
またそれらから学んだことを活かして,新しい実践や理論の形を模索しています。
逆SSTは定型にはなかなかぴんと来ず,気づかれなかったり誤解されたりする発達障がい者の振る舞いを理解するための工夫の一つです。昨年は研究所のイベントとして3回行ったほか,渡辺主席研究員や私が,それぞれ大学の講義でも実施しました。NPO法人全国精神障害者地域生活支援協議会【あみ】のみなさんなど,外部の方からの実施依頼もぼちぼち入り始めています。今年もこの逆SSTに工夫を加えながらさらに続けていきます。
では当事者の視点を大事にするというのはどういうことでしょうか。これまでの障がい理解だけではなく,なぜそのような視点が必要なのでしょうか。
昨年はまずは相互理解が難しいことが多い自閉の問題を取り上げ,当事者の視点を大事にした対話的相互理解の基盤を理論的に整理する,という作業にも取り組みました。山本と渡辺主席研究員,大内雅登非常勤研究員の共著で,この成果がこの春,日本質的心理学会の学術誌「質的心理学研究」(22号:新曜社刊)に「説明・解釈から調整・共生へ:対話的相互理解実践にむけた自閉症をめぐる現象学・当事者視点の理論的検討」というタイトルで掲載されます。
この問題への取り組みに当事者との対話が欠かせないのは,定型発達者が自分のそういう視点でいくら「障がい」理解しても,やっぱり障がい者が日々体験していることはうまく理解できず,自分の見方で勝手に思い込んでしまうからです。昨年の逆SSTでは,現役のカウンセラーなどいわゆる心理学的な臨床に携わる方たちにも回答者として参加していただき,自閉当事者の思いにどこまで迫れるかに挑戦していただきましたが,やはりなかなか理解できませんでした。
発達障がいにかかわる発達心理学や,コミュニケーションに関わる分野の研究者も同じです。それらの理論もまた「一般的な=定型的な」視点から作られているため,当事者視点を上手くくみ取れていない部分がたくさんあります。だから当事者とある意味で対等な立場で一緒に問題を考えていく必要があるのです。
この春,私たち(大内・山本・渡辺)が編者となり,一つの本を出します。自閉当事者の大内さんの子ども時代からの体験談や,大内さんが発達障がい児の支援に携わっていて考えることなどを紹介してくれた文章について,発達心理学・ナラティヴ研究からの展開としてのもの語り研究・人類学・当事者研究・談話分析などの第一線で活躍されてきた研究者の皆さんに,それぞれの視点から論じていただき,そこからこれからの自閉理解の新しい方向性を模索していく本を出します。みなさん大内さんと対話をするような素晴らしい論考が集まり,とても魅力的な本になったのではないかと思います。
そんな「異質さを持ったもの同士」の対話的相互理解を進めていくために,大学ではどんな教育が可能でしょうか。山本が今年度駒沢大で社会学の学生さんを相手に行った「異文化コミュニケーション論」では,逆SSTの実施を含めて,いろいろな角度から工夫をしてみました。その内容と,それによって受講生の皆さんに生まれた変化について,「異質なもの同士の対話的関係調整を目指す授業実践の効果」という論文も書いてみました。これもこの春に出ることになるかと思います。
そんなふうに,実践的にも理論的にも少しずつ足場固めをしている中で,昨年末には東大先端研で当事者研究を展開されている熊谷晋一郎研究室が主宰されている新しい支援システムの開発に関わる研究プロジェクトにも声を掛けていただき,すでに協力が始まっています。
研究所が始まって7年がたちましたが,ようやく「研究所」らしい活動の足場固めができてきました。これから現場の皆さん,当事者の皆さんと一緒に,さらに次の一歩を踏み出していければと思います。
どうぞみなさんもこの研究所の活動にもいろいろな形でご参加・ご協力ください。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
- 感じ方の違いを超える対話的支援
- 支援を当事者視点から行うって何のこと?
- 支援としての趣味の語り合い
- R君の積み木(13) 調整する力の育ち
- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生
- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある
- 自閉系の方がマニアックになる時
- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる
- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと
- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ
- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす
- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる
- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ
- 間違いではなく,視点が違うだけ
- 今年が皆さんにとって良い年でありますように
- 母子分離と不安 ③
- 母子分離と依存 ②
- 母子分離と依存 ①
- 支援者こそが障がい者との対話に学ぶ
- 「笑顔が出てくること」がなぜ支援で大事なのか?



投稿はありません